この記事は約5分で読むことができます。
イタリア語で「分散したホテル」を意味する「アルベルゴ・ディフーゾ」は、宿泊者がそのまち全体を楽しむことができると、今とても注目されています!
宿泊者側にも地域側にも双方大きなメリットがある「アルベルゴ・ディフーゾ」はスローシティの考えのもとに生まれた、新しい宿泊形態です。
今回はそんな「アルベルゴ・ディフーゾ」について解説していきます。
- 人が減って寂しきなってきた地元を盛り上げていきたいと考えている方
- 空き家が増えて困っている方
- 観光客をまちなかに呼び込みたいと考えている方
- 観光業や不動産関係にお勤めの方
- 地元を堪能できる、いつもよりちょっと変わった観光を楽しみたい方
- ゆっくりのんびりと旅行を楽しみたい方
- 旅先でいろんな人と交流してみたいと考えている方 など
目次
地域の空き家を活用した「アルベルゴ・ディフーゾ」のしくみ
アルベルゴ・ディフーゾは、既存の廃屋や店舗をリノベーションし、客室、レストラン、バー、レセプション(受付)、土産店など、各機能をそれぞれの空き家が担うかたちとなっています。
増える空き家を外観や造りは変えず、客室はベッドやバスルームを整え、旅行者がくつろげる空間にします。
受付や食堂が地域に一か所あればよく、食事は、地元のレストランで楽しんでもらえばいいという発想です。
そうすることで、まち全体をあたかもひとつのホテルのように設計しています。
たとえば、アルベルゴ・ディフーゾを訪れた旅行者は、レセプションでチェックインをし、宿泊先の鍵を受け取ります。
そして、地域内のレストランで食事をしたり、食材を購入して宿泊先の部屋で調理をしたり、もちろん地域の景観や人々との交流も含め、まちの滞在時間を楽しみます。

地域を回遊してもらう画期的なシステム
「アルベルゴ・ディフーゾ」を提唱したのは、イタリア各地で地方創生に尽力されてきたジャンカルロ・ダッラーラ教授であり、彼はイタリア・アルベルゴ・ディフーゾ協会の会長も務めています。
1976年に北イタリアのフリウリ地方で発生した大地震により、ある集落が廃村の危機の直面。その村を復興させるべく試行錯誤を重ねた結果、ひとつひとつの空き家を宿として提供し、まちぐるみで地域を盛り上げることにしました。
そもそもイタリアでは、農村に泊まって、澄んだ空気と地元の旬の料理を味わい、乗馬やトレッキングを楽しむような農家民宿「アグリティズモ」が盛んでした。
そこで、その農家民宿を発展させた「アルベルゴ・ディフーゾ」という新しい宿泊システムが生れました。
「アルベルゴ・ディフーゾ」はまちぐるみで構築しているために、訪問者の回遊を自然に促しながら、まるでその地域に暮らしているかのような気分を堪能してもらうことができます。その結果、ロングステイやリピート率の向上も期待できるのです。

地域に今ある「本物の暮らし」を大切にする
アルベルゴ・ディフーゾの最大の目的は、高齢化が進み、若者が都市へ移り、空き家が増えていく地域を存続させ、活性化させることにあります。
一方、普通のホテルでは、まず観光客の快適さが要求されるため、狭い階段、低い天井などがあれば、取り壊して新しく造ります。そこには地域の生きた暮らしはもうありません。
これに対し、アルベルゴ・ディフーゾは、今そこにあるものを壊さない、できるだけそのまま活かす。
ですから、雨の降る日は、レセプションから宿への移動は億劫だし、狭い階段や低い天井など、宿泊客も多少の不便を受け入れなければならない。
けれども、その代わりに保証されるのは、その地域の「本物の暮らし」です。
そしてその魅力を地域全体で味わうことができるのです。

交流を重視した「スローな観光」の実現
アルベルゴ・ディフーゾには、「生きた暮らし」があり、「スローな観光」を堪能できます。
「スローな観光」とは、最低でも2~3泊はして、山の小道を散策したり、海で遊んだり、本当においしいものを食べたり、のんびり過ごすような、地域の「本物の暮らし」を楽しむ観光です。
それは、大型バスで、決められた店で慌てて買い物をし、決められた食堂でぱっとしない食事をし、決められた宿に詰め込まれ、慌てて次へと移動するせわしない旅ではありません。
地域をじっくりと回り歩き、地元のいいものには、きっちりと対価を支払う。
それが理想的な旅のスタイルとなっています。
観光もそろそろ量から質への転換期なのです。
さらに、アルベルゴ・ディフーゾによって、地域全体を活性化し、地域の雇用も増やすことができます。

日本の観光地では、宿泊者はまちを出歩かない!!
日本の観光地にあるホテルや旅館では、チェックインしたあと、その宿泊施設内の温泉や大浴場に行き、その後部屋の中や食堂で豪華な食事を堪能し、自分の部屋で就寝するという流れが一般的です。
そのため、一度宿泊施設の中に入ったらそのまちを歩き回ることはほとんどありません。
周辺にあるお店はだいたい午後5時や6時ごろには閉店してしまい、まちなかは真っ暗となります。
そのため各宿泊施設が観光客を囲い込みをしているような状況であり、それでは地域全体が活性化することはありません。
一方、「アルベルゴ・ディフーゾ」のシステムの導入すれば、宿泊者はまちなかを回遊することとなります。
そのため、地域の経済が積極的に回るようになるのです!
周辺のレストランやバー、カフェ、土産物屋、工芸品店、銭湯などに観光客が訪れるようになり、地域全体が活性化され、さらにお店が増えていくことで、どんどんと面白い地域となり、観光客が増えていくようになるのです。
「アルベルゴ・ディフーゾ」のシステムを導入した宿泊施設
旅行客の訪問や賑わいがなくなってしまった地域を、リノベーションを含めてまちぐるみで開発し、アルベルゴ・ディフーゾのようなかたちで再建することも可能かでしょう。
このような仕組みはすでに日本でも取り入れられています。
商店街ホテル 講 大津百町(滋賀県大津市)

昔ながらの商店街に、町屋をリノベーションした客室が点在していることが特徴です。
宿泊者はこの部屋を拠点として、ラウンジでくつろいだり、レストランで食事をしたり、総菜を買って部屋に持ち帰ったりなど、まち全体を楽しむことができます。まさにアルベルゴ・ディフーゾの日本版です。
ホテル「hanare」(東京都台東区谷中)


フロントでチャックインすると「散策マップ」と「銭湯のチケット」がもらえる仕組みがあります。また、レンタサイクルも借りられるので、自転車や徒歩で周辺を散策しながら、商店街や路地の雰囲気を味わうなど、周りのアクティビティが繋がっています。
SEKAI HOTEL 布施(東大阪市布施)

駅近くの商店街の中に店舗をリノベーションしたホテルのフロントがあります。
フロントで渡されるパスを商店街の中にある提携店で見せると、各々の特典が受けられるという仕組があります。
東大阪市ならではの町工場体験ができるようなプランも用意されています。
OMO5京都三条(京都市)

有名な星野リゾートが手掛ける、2021年4月15日にオープンしたばかりのホテル。
京都三条の「レトロでオシャレな街歩き」を宿泊者には堪能してもらうため、OMO5には小さなカフェはありますが、レストランはありません。そのため、食事は基本的にホテル周辺の飲食店で行うことになります。フロントにある大きな地図には、スタッフがおススメする店舗の情報が掲載されています。その他、京都の街なかを堪能できるアクテビティがたくさん用意されています。
このように、アルベルゴ・ディフーゾの仕組は、これからのまちづくりや場づくりの参考となります。
特定のまちや地域に着目し、まちづくみで開発を進めていくことが、今後は増えていくかもしれません。
そのような仕組みにおいても、重要なのは空間(場)と運営、そして人と人とを繋げる工夫なのです。
あなたは、自分が住んでいるまちで本当に「やりたいこと」をできていますか?
↓↓↓やりたいことを実現させる具体的な方法は以下↓↓↓
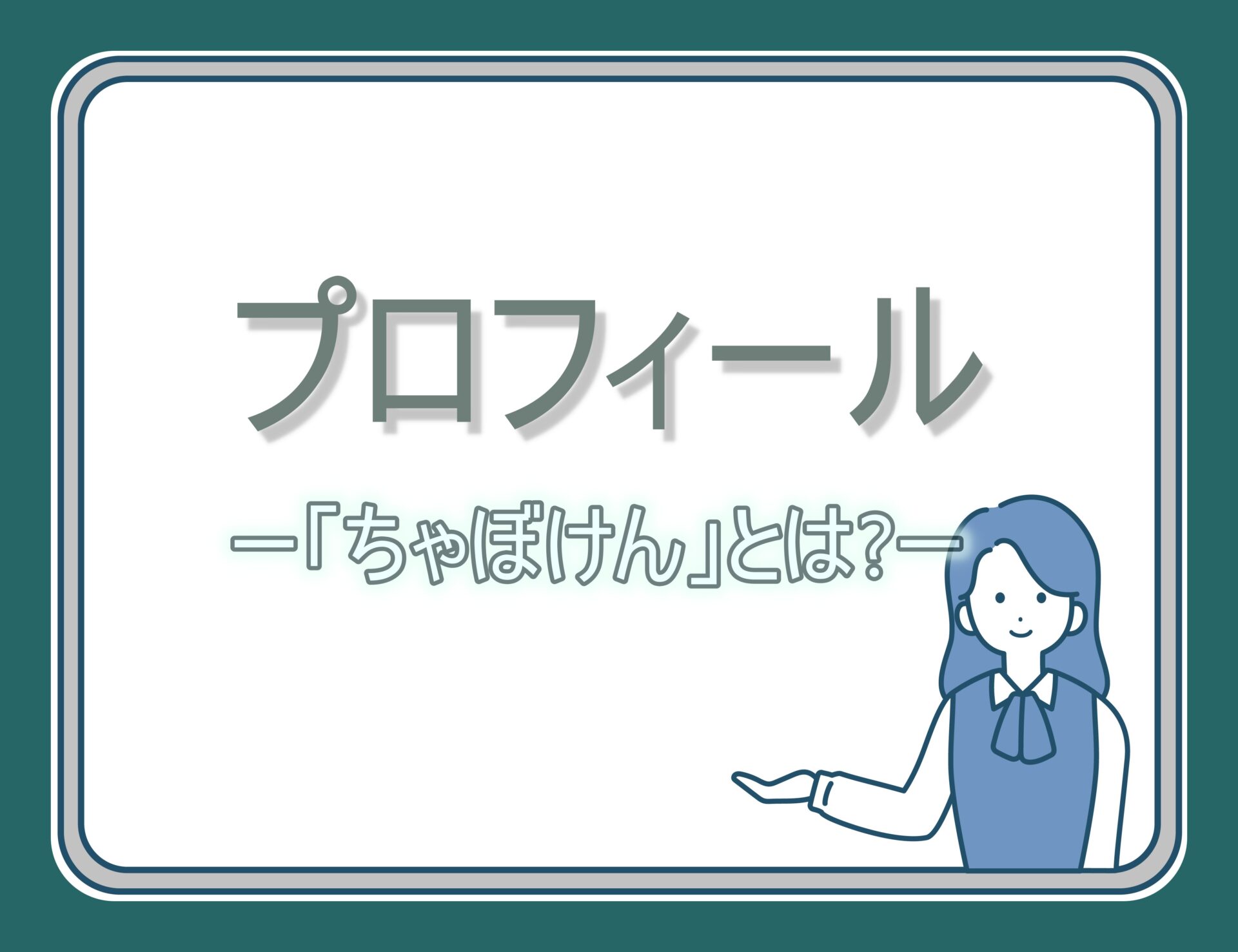

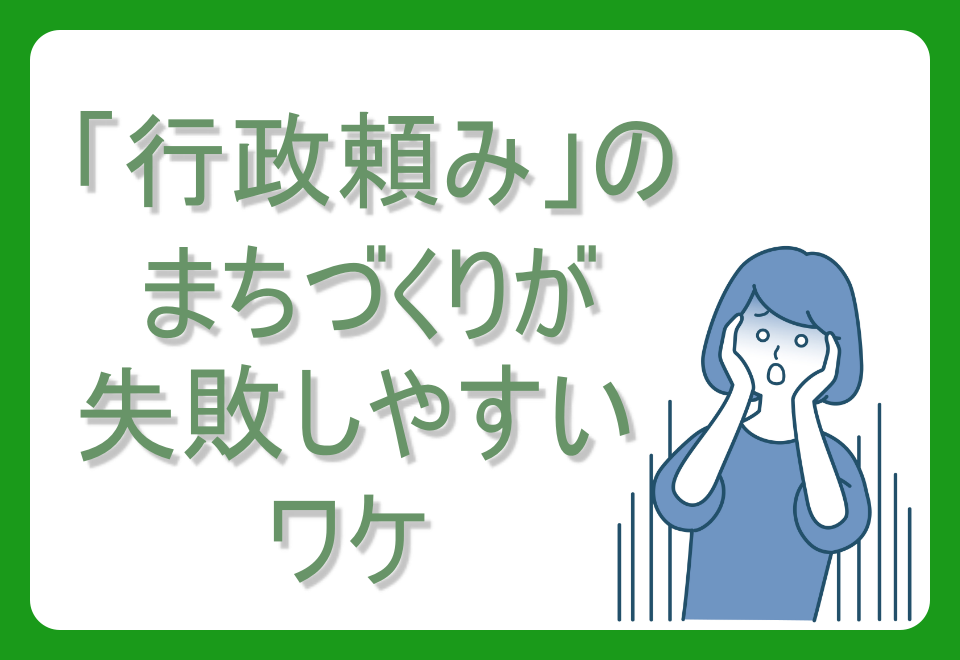








あなたは「アルベルゴ・ディフーゾ」を知っていますか?