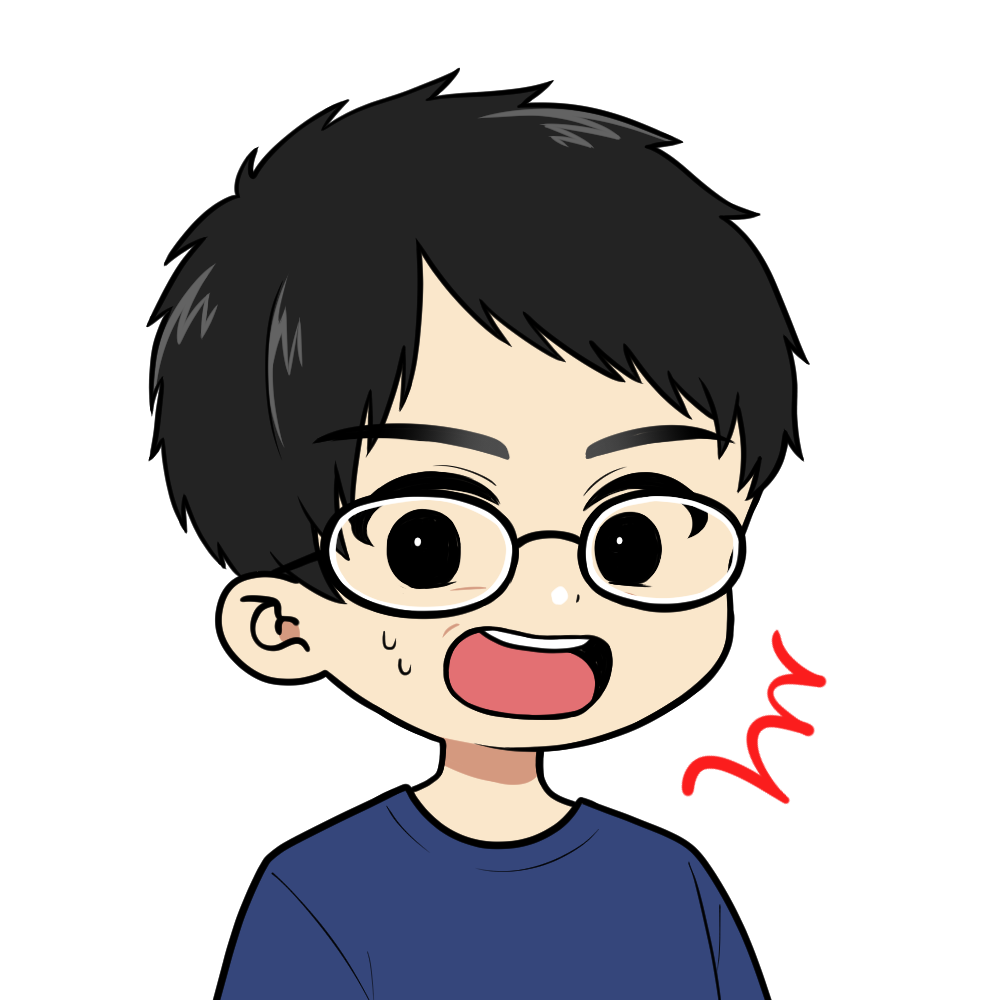
‟指定管理者制度”って知っていますか?
おそらく、
あなたの近くにある公共施設もこの指定管理者制度を導入していることでしょう!
‟指定管理者制度”は、
公共施設などの管理・運営を自治体に代わって民間企業などが行う仕組み
のことです。
公共施設のサービス向上などを目的として、2003年に開始され、
今では、なっ、なっ、なんと・・・
延べ7万を超える施設で活用されています!
いまや、あらゆる施設で導入されているこの指定管理者制度ですが、
実は様々な問題点を抱えているようなのです!
いったい、どういうことなのでしょう?
これを知っておかないと、
あなたの地域の公共施設は大変なことになるかもしれませんよ!
今回はこの指定管理者制度のメリット・デメリットや問題点、失敗の原因など
について解説していきます。
- 図書館や美術館、児童館などの公共施設をよく利用される方
- 地域の公共施設の実態について知りたい方
- 指定管理者制度について詳しく知りたい方
- 公園や図書館などの公共施設の有効活用について興味がある方
- 最近、公共施設のサービスが変わってきたと感じている方 など
目次
そもそも「指定管理者制度」とは?
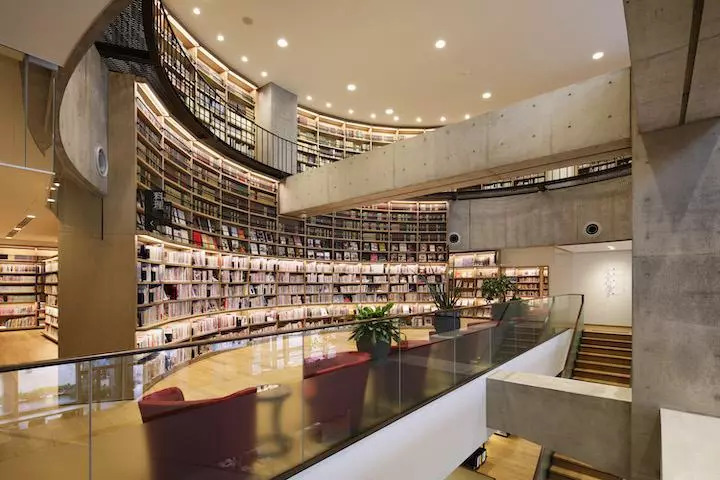
指定管理者制度とは、
自治体が所有している公共施設を、
施設経営のノウハウがある民間事業者(株式会社、NPO夫人、学校法人、医療法人等)に管理してもらう制度のことで、
地方自治体と民間企業が連携してまちづくりを進める「公民連携」の一つです。
自治体から支払われる指定管理料をもとに、
民間事業者が公共施設を管理・運営を行うのが一般的です。
指定管理者制度により、民間事業者に管理を委託できる公共施設は、
体育館や運動場、プール、博物館、美術館、図書館、コミュニティーセンター、福祉施設、保育園、公立病院、公園、学校などです。
指定管理者制度の代表といえば、
TSUTAYAで知られているカルチュア・コンビニエンス・クラブが管理運営している「ツタヤ図書館」が有名でしょう!
賛否両論のあるツタヤ図書館ですが、
「地元の図書館がオシャレになった!」「羨ましい!」
などの声が多くあがり、
これにより「指定管理者制度」というものが世間に広く知れ渡ることになりました。
TSUTAYA図書館に協業企業が呆れた理由-CCCとの公立図書館運営の協業見直しへ(東洋経済ONLINE)
さて、
一見うまくいっているように見える「指定管理者制度」ですが、
全国的にみると必ずしもそうとはいえない状況になっています。
それはいったいどうゆうことなのでしょうか?
指定管理者制度のメリット、デメリット

そもそも自治体が指定管理者制度は採用するメリットはどこにあるのでしょうか?
指定管理者制度を導入するメリット
①経費の削減
各自治体が指定管理者制度を導入する、主な理由は「経費削減」です。
どこの自治体も人口減少などの影響により、税収が減少し続けており、
その結果、
公共サービスの低下や公共施設そのものの存続が危ぶまれています。
そこで、経営ノウハウがある民間事業者に管理・運営を任さることで経費削減ができるということです。
指定管理者を選定するときは、公募により民間事業者を募り、事業者同士で競わせます。
いろんな要素によって指定管理者が選ばれるのですが、そのときもちろん、指定管理料が少ない事業者が高く評価される仕組みになっているのです。
②公共サービスの向上
経費削減以外の主な理由としては、民間事業者に管理・運営を任せることで、
「市民のかゆいところに手が届き、公共サービスが向上するだろう」という狙いがあります。
民間事業者に管理・運営を任さることで、これまでに蓄積したノウハウを公共サービスに活かすことが期待されています。
民間事業者には、自治体職員には思いつかないような企画力やアイデアがあり、従来とは違ったサービス提供を行うことで、多様な住民ニーズに応えやすくする狙いがあります。
指定管理者制度を導入するデメリット
メリットがあれば当然デメリットもあります。
指定管理者制度で考えられているデメリットとはどういうものなのでしょうか?
①自治体の運営意識の低下
サービスを提供するのは指定管理者の民間事業者ですが、公共施設を所有しているのはあくまでも自治体です。
指定管理者制度を導入することで、最終的に責任を持つべき自治体の意識が低下することが懸念されています。
また、市役所職員が市民と直接顔を合わせる機会が減少しますので、問題や要望が自治体に届きにくくなる可能性も十分に考えられます。
②指定管理者変更によるサービス低下
指定期間が終了すれば、指定管理者が変更する場合もあります。
そのとき、「提供されるサービスが同じように継続されない」ことも十分にあり得ます。
「運営方法がコロコロと変わる」
「指定管理者が変わってサービスの質が悪くなった」
なんてことも起こりえるのです。
サービスの質の担保できるかどうかが大きな問題となってきます。
指定管理者制度で管理費が削減できる理由

「指定管理」はいわば「外注」です。
例えば、「行政が管理運営に5千万円かかっていた公共施設の管理を、民間事業者に4千万円で任せる」というものです。
しかし、いったいなぜ民間がやるほうが安くなるのでしょうか?
それは、効率的に業務を行うようになるから、
というものもありますが、一番の理由は「人件費が抑えられるから」です。
どこの地方でも、公務員は高給取りです。
余程の大企業の支社でもあれば別ですが、
大抵の地方では民間企業の社員の平均給料は公務員より圧倒的に安いです。
つまり施設運営を公務員にやらせるより、
民間人にやらせたほうがコストカットできるので、安くなるわけです。
浮き彫りになってくる指定管理者制度の問題点

指定管理者制度ができて20年近く経とうとしています。
実際、指定管理者制度が導入されている公共施設は今、
どのようになっているのでしょうか?
各地の公共施設ではいろいろな問題が表面化してきているようです!
指定管理者制度というのは、
名目上は「民間のノウハウやアイデアを公に活かしながら、施設の魅力的な経営を実現する」ということで、いろんな自治体で採用されています。
ところが・・・
指定管理者制度が導入する自治体が考えていることは、
やはり「なんとかして経費を削減したい」ということが一番でしょう。
それほど、地方の自治体によって、”税収が減ってきている”ことは深刻な問題となっています。
そして、自治体が経費削減を優先することによって、
今、各地の公共施設では様々な問題が起きているのです!
さらには、地域によっては
「行政予算に依存する民間を生み出す」という構造になっているものが多くあります。
指定管理者制度の失敗の原因とは?

実際、経費削減を優先させすぎると、どのような問題が起きるのでしょうか?
課題① 現場スタッフが薄給で疲弊している
先日、NHKで「政令指定都市にある児童館の館長が年収250万円未満である」という報道がされました。
勤務は1日9時間、週6日程度。休日はなんと月に4日だけ!
この低賃金の背景には指定管理者制度による経費削減が主な理由であり、この実態を自治体が貧困者を生み出している、いわば「官製ワーキングプア」と指摘しています!
官製ワーキングプア?-「年収250万円未満」児童館館長が訴える公共施設の”危機”(NHK)
自治体は経費削減を優先するため、指定管理料は管理・運営ができるギリギリの額とされることが一般的です。
そのため、真っ先に削られるのが、現場で働くスタッフの人件費です。
現場のことを知ろうとしないまま、公共施設の管理・運営の予算が決められてしまうと、このような事態を巻き起こしてしまいます。
課題② サービスの質が低下する恐れがある
指定管理者制度は、
単に管理予算を削減するだけではなく、市民への公共サービスの向上も重要な目的の一つです。
そのため、指定管理者である民間事業者が、公共施設に新たにテナントを入れたり、有料セミナーを開催したり、電力代の削減を行ったりして、収支を改善していくことができれば、民間に外注する意味もあります。
しかし、実際の業務内容などは入札の際に役所のつくったルールにがんじがらめになっていて、自由に経営改善できないケースが多々あります。
指定管理料は減ることがあっても、増えることはほとんどありません。
そのため、現場スタッフの給料が減らされるか、サービスの質を低下させるを得ないのが現状です。
課題③ 特定の業者が儲かる仕組みになっている
指定管理料が低く割に合わない条件でも、引き受ける地元企業や、地元の第三セクターや自治体の外郭団体が受けていることもあります。
時には、それらの団体の支援のために、自治体があえて外注している場合もあり、極めて不健全な構造になっています。
これでは単なるコストカットに留まるか、悪くすれば官民の癒着につながってしまいます。
全ての公共施設でそのようなことが起きているわけではありませんが、場合によっては天下り先の確保のために、指定管理者制度が使われているケースもあるのです!
失敗させない指定管理者制度の工夫とは?
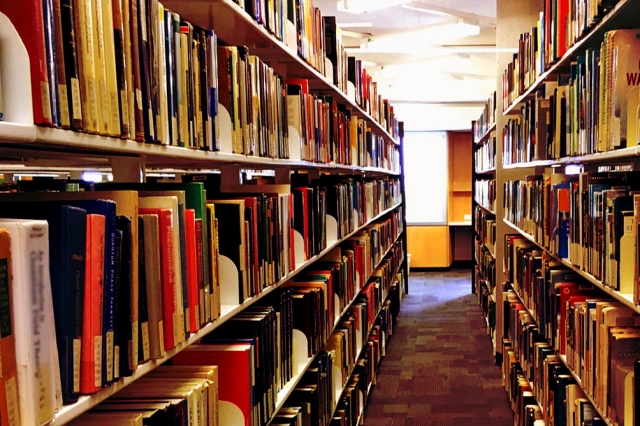
自治体が指定管理者制度を導入するとき、「あれはダメ、これはダメ」といろんな規制を設けてしまうと、
民間事業者が自由な発想やアイデアで市民サービスを提供することができなくなり、
単なるコストカットになってしまいかねません。
指定管理者制度を設けるときは、
「民間に管理を委託する」というよりも、
「施設を使ってもらって面白いことをしてもらう」という視点が必要となります。
行政のルールを柔軟に運営し、公共施設を活力ある民間に任せれば、
公的施設を創造的な場所に変えていけます。
実際、各地でそのような実例もたくさんあります。
指定管理とは違った方法で、
廃校になった建物内にシェアオフィスやカフェなどの複数のテナントを入れたり、
イベントスペースをつくってレンタルすることで売上を上げているところがあります。
指定管理制度にもとづいて、かんじがらめで管理させるよりも、
利用条件などを緩和し、貸し出したり売却したりして、
民間の知恵を活かして自由に運営してもらったほうが、
面白い転換になることが事例からもわかります。
ワクワクする仕掛けがないと人はわざわざ来ません!
民間のアイデアを十分に活かすことのできる方法を考えていく必要があるのです。
まずは指定管理者制度のメリット・デメリットを知ろう!

指定管理者制度の‟負の側面”として、
民間事業者の「地域に貢献したい!」という想いを利用して、
“行政が民間を搾取する”という部分があります。
または、
「行政の支援がないと維持・存続ができない」ダメな民間企業を生み出してしまう可能性もあります。
いずれにしても、このような状況で最も痛い目に遭うのは、私たち市民です。
適切な管理・運営ができていない公共施設は数年後に潰れるか、赤字を税金で補填するか、公共サービスの質を下げるか、という選択をせざるを得ないからです。
‟官製ワーキングプア”が出現していたり、
‟官民の癒着”が常態化している地域は、かなり危機的な状況と言えるでしょう。
今は現場のスタッフの犠牲によって管理・運営が成り立っている公共施設も、
その状況が長続きするはずがありません。
そんな公共施設はいずれは潰れてしまうでしょう。
例えば、児童館は子どもの遊ぶ場所を提供するだけではなく、
子どもの見守りをしたり、
変わった様子の子がいれば学校と連携を取り合って対応したりします。
また、悩みを抱えている子どもや保護者から、
昼夜を問わず相談の電話がかかってくることもあります。
そういった専門性の高い仕事の人でさえ、低い給与で働いている実態があり、
こういった施設が無くなったり、サービスの質が低下することによって、
困るのは誰でしょうか?
この先、日本中のあらゆる自治体で税収がどんどん減っていきます。
そのため、これからも今までの同じ質、同じ量の公共サービスを受け続けることは不可能と言っていいでしょう。
自治体も様々な工夫を考えており、
指定管理者制度は民間の力を借りながら、
公共施設のサービスを維持・向上させる取り組みとして注目されています。
しかし、実態は理想とはほど遠く、
「行政が民間を安いお金で使う」という問題があるのです。
指定管理者制度を導入して、
「施設スタッフの対応が丁寧になった」
「営業時間が長くなった」
「システムが充実した」
「家族で楽しめるイベントが行われるようになった」
などの理由から、利用者が数倍に伸びた施設もあります。
しかし一方で、
施設の存続が危ぶまれているほど危機的な状況でありながら、
その実態をあまり市民に知られていない公共施設もあります。
地域の公共施設は、限られた指定管理料の中、
現場のスタッフの高い志によって、その公共サービスが支えられている。
今後の公共施設のあり方、
市民サービスの向上という本来の目的を達成させるためにどうしたらいいのか、
住民を巻き込んだ議論が必要になっています。

あなたは、自分が住んでいるまちで本当に「やりたいこと」をできていますか?
↓↓↓やりたいことを実現させる具体的な方法は以下↓↓↓
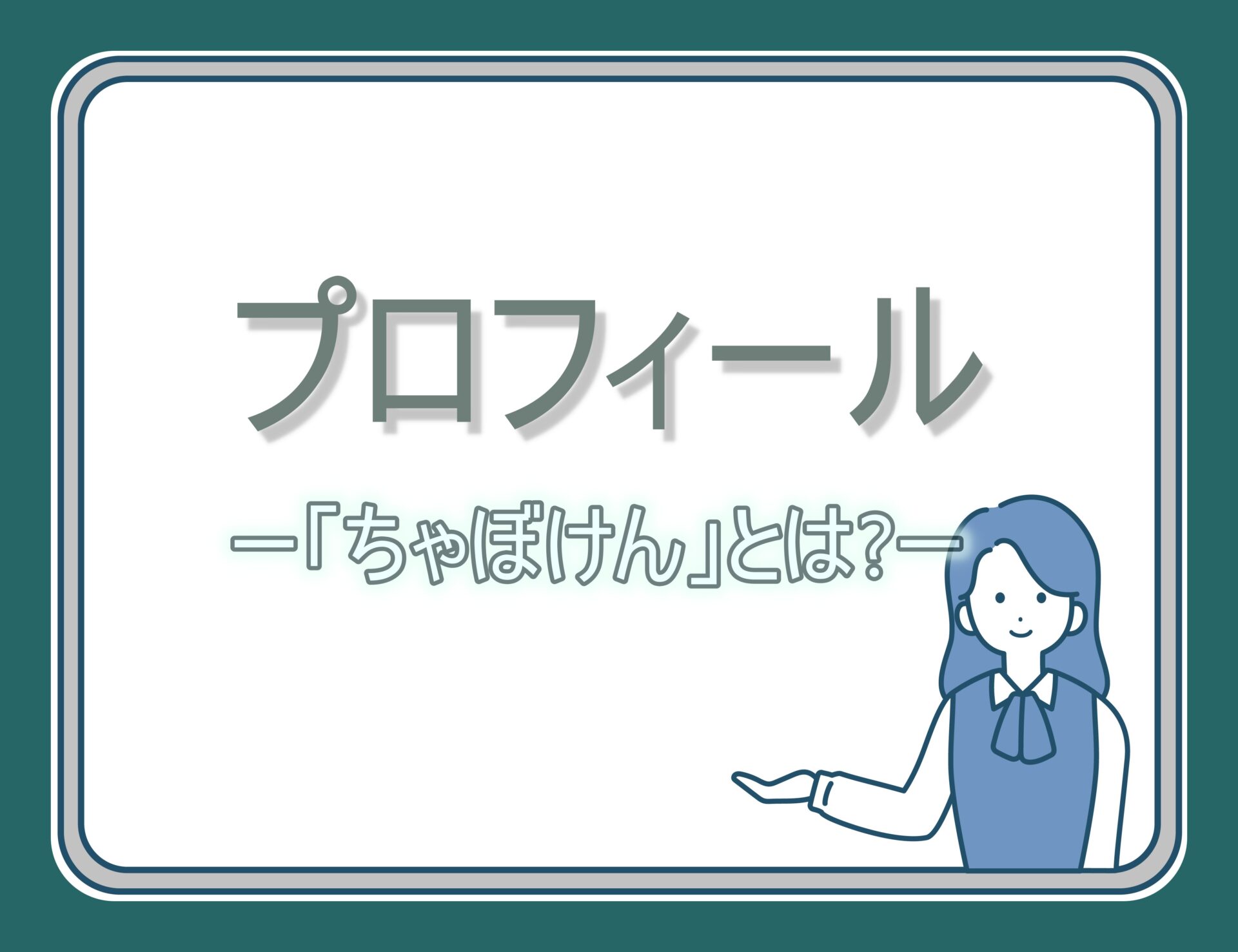

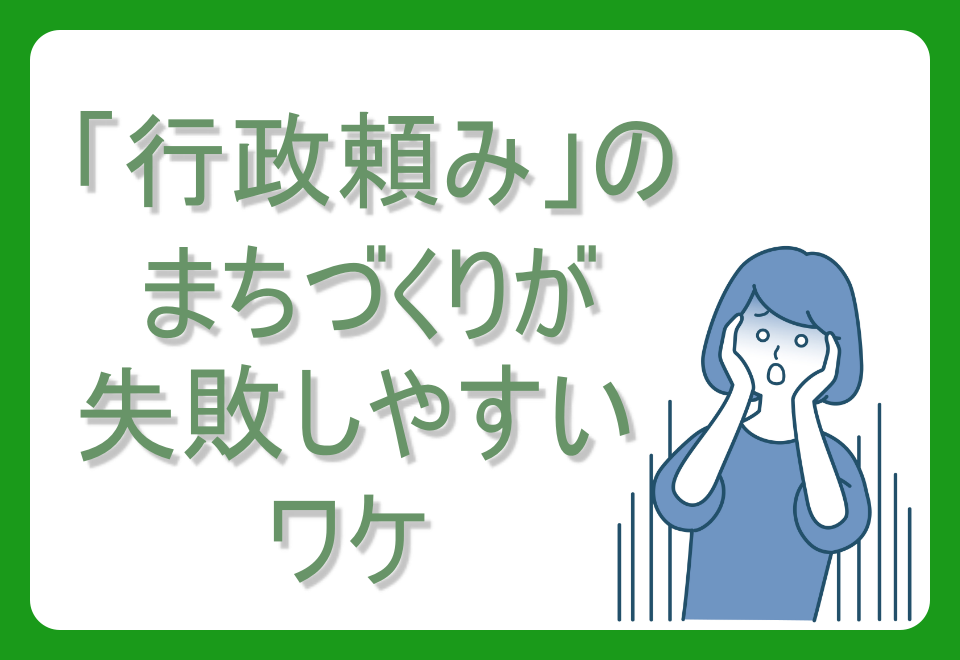







指定管理者制度のディメリットについて、大変勉強になりました。
鎌倉市放課後学童保育「かまくらてらっ子」設けられたことによって、学童の親御さんは安心して就労でき感謝しておりますが、昨年、一昨年と2年引き続き指定管理者の企画提案プログラム[自衛隊 体験教室]を監督官である鎌倉行政青少年課は検討もなく実施してしまいました。親御さんはじめマスコミが大きな記事で取り上げ、行政窓口に苦情が出ています。行政窓口は「自分たちは不適切なことは一切していない」と豪語するばかりです。なにも判らない学童に対して軍事教練まがいのものを洗脳して良いものだろうか?職員行動憲章に反していることを平気で行っているが…….
コメント、ありがとうございます。
指定管理者制度はとても便利な制度で今や身近な存在となっていますが、
残念ながら良い面、悪い面含め具体的なことはあまり知られてはいません。
そのため、知らないうちに管理者や運営者が変わっていた、
ということがよく起こります。
そして、ルールが自治体によってバラバラなのが実情で、
行政の責任が曖昧になってしまうという側面もあります。
さらに、もし何か問題が起きてしまったときに一番に影響を与えてしまうのが、
一般市民の方であり、特に子どもたちのような立場が弱い人たちです。
なぜなら、問題は往々にして立場の弱い人のところで発生しますので・・・
プログラムが実施されている意図がわかりかねる部分もありますが、
皆さんが危惧されているのも、このようなことではないかな、と思います。
多くの人が制度のメリットとデメリットのそれぞれを理解したうえで、
適切なルールづくりをする必要があると考えており、
そのために、今後もできるだけわかりやすい情報発信を行っていく所存です。
皆様のお住いの地域がよりよいものとなりますよう、
心からお祈り申し上げます。